この記事を執筆・監修した人

近年、育児や介護をしながら働く人が増える中で、「仕事と家庭の両立」は多くの企業にとって重要な課題となっています。特に中小企業では、社員が安心して出産・育児・介護を両立できる環境を整えるための制度導入や仕組みづくりが急務となっています。
こうした取組を支援するために厚生労働省が設けているのが「両立支援等助成金」です。
本記事では、両立支援等助成金の制度概要から各コースなどについてわかりやすく解説していきます。
詳細や最新の情報は、厚生労働省ホームページを確認するようにしてください。
リンク:両立支援助成金
両立支援等助成金とは

両立支援等助成金は、仕事と家庭の両立を図るために職場環境の整備や制度導入に取り組む事業主に対して、国がその費用の一部を助成する制度です。
主な目的は、育児・介護・不妊治療などによる離職を防ぎ、誰もが安心して働き続けられる職場づくりを推進することにあります。
助成対象となる取組内容は多岐にわたり、
- 育児休業を取得しやすくする仕組みの導入
- 職場復帰支援プランの作成
- 短時間勤務制度や在宅勤務制度の導入
- 介護休業制度の整備
- 不妊治療と仕事の両立支援
など、企業が従業員のライフステージに応じて柔軟な働き方を整備する際に活用できる制度です。
制度設立の背景

日本では、少子高齢化の進展に伴い、労働力人口の減少が大きな社会課題となっています。厚生労働省によると、出産・育児を機に離職する女性は依然として多く、また介護を理由に離職する中高年層も増加しています。
これらの離職を防ぎ、仕事と家庭を両立できる社会を実現することは、経済成長と人材確保の両面から急務です。
そのため、国は育児休業制度の普及・定着を支援する「両立支援等助成金」を2005年度に創設し、以後、社会情勢に応じて改正を重ねながら継続して実施しています。
特に2022年の育児・介護休業法改正以降は、男性の育休取得促進や柔軟な働き方の導入支援が重視され、助成対象が大幅に拡充されました。
この制度は、単なる経済的支援ではなく、「企業文化の変革」を促す施策として位置づけられています。
6つのコースについて

以下に、各コースの詳細について解説していきます。
出生時両立支援コース
男性の育児休業取得率を高め、育児を夫婦が協力して担える社会を目指すためのコースです。出生直後からの父親の育児参加を支援し、男性社員が子の出生後8週間以内に育児休業を取得できるよう、企業が職場体制を整える場合に助成されます。
単に「制度を整える」だけでなく、取得しやすい雰囲気づくりや業務の引継ぎ体制整備など、実際に男性が休める企業文化の醸成を目的としています。
主な支給要件
- 男性労働者が子の出生後8週間以内に育児休業を取得(5日以上などの基準あり)
- 企業が育児休業の取得を促すための雇用環境整備・業務体制整備を行っていること
- 社内方針を周知し、上司・同僚に対して理解促進のための研修や説明を実施していること
介護離職防止支援コース
家族の介護を理由に退職する“介護離職”を防ぐことを目的としたコースです。介護休業や短時間勤務などの柔軟な勤務制度を導入し、介護と仕事を両立できる環境を整えた事業主を支援します。
近年は40〜50代の従業員の介護負担が増加しており、中堅人材の離職を防ぐための人材維持施策として注目されています。
主な支給要件
- 「介護支援プラン」を策定し、本人・上司・人事の三者面談を実施していること
- 介護休業を連続5日以上取得した社員が復職していること、または介護短時間勤務などの制度を実際に利用していること
- 介護休業制度や相談窓口を就業規則等に明記・周知していること
育児休業等支援コース
育児休業を取得する従業員が、スムーズに職場復帰し、長く働き続けられるよう支援するコースです。企業が育休者に対して復帰プランを策定し、面談・情報提供・原職復帰支援などの一連の取組を行う場合に助成されます。
特に女性社員のキャリア継続や、育休復帰後の離職防止を目的としており、職場の“育休後支援文化”の定着が求められます。
主な支給要件
- 育児休業を取得した従業員に対して「職場復帰支援プラン」を作成
- 休業前・休業中・復職前・復職後の4段階で面談・フォローを実施
- 復職後、原職等に申請日までの間6か月以上継続勤務していること
育休中等業務代替支援コース
育児休業や短時間勤務を取得する従業員の代替要員を確保し、業務負担を軽減するための企業を支援するコースです。代替要員の新規雇用や社内での業務分担、代替手当の支給などを行うことで、育休取得を妨げない組織体制の整備を目的としています。
中小企業では特に人員不足が課題であり、現場の「休ませたくても休ませられない」を解決する制度です。
主な支給要件
- 育休取得者または短時間勤務利用者の代替を行う社員への手当支給、または新規雇用を実施していること
- 代替期間や勤務実績が一定期間(例:最短で7日以上~14日未満)あること
- 手当支給や雇用契約が就業規則等に明記されていること
柔軟な働き方選択制度等支援コース
在宅勤務、フレックスタイム、時差出勤、短時間勤務など、多様で柔軟な働き方を導入・定着させた企業を支援するコースです。育児や介護だけでなく、ライフステージに応じて働き方を選べる制度を設けることで、ワークライフバランスと生産性向上を両立することが狙いです。
テレワークやサテライトオフィス勤務など、DX推進とも親和性が高く、企業の魅力向上にもつながります。
主な支給要件
- 柔軟な働き方制度(フレックスタイム・時差出勤、在宅勤務、短時間勤務など)を3つ以上導入
- 対象制度利用者が、制度のうちの1つを、利用開始から6か月間で一定の基準以上利用したこと
- 就業規則や社内規程に明文化し、全社員に周知していること
不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース
不妊治療、月経困難症、更年期障害など、女性特有の健康課題に対応した職場環境整備を行う企業を支援するコースです。近年は、女性が健康上の理由で退職やキャリア中断を余儀なくされるケースが増えており、健康課題と就業の両立支援による離職防止が目的です。
不妊治療に限らず、女性社員が安心して相談できる社内体制の整備、休暇制度の新設、理解促進研修なども評価対象となります。
主な支給要件
- 不妊治療や健康課題に対応する休暇制度や勤務配慮制度を導入
- 相談窓口を設け、プライバシーに配慮した運用を行っていること
- 実際に社員が制度を利用した実績があること
これら6つのコースは、「育児・介護・健康」などライフイベントに対応した“働き続けられる企業づくり”を後押しする制度です。いずれも「制度導入+実際の利用」が共通要件であり、形式的な整備だけでは支給されません。就業規則の改定・面談記録・復職確認など、エビデンス管理の徹底が求められます。
雇用関係助成金に共通する支給要領について

両立支援等助成金は「雇用関係助成金」の一種であり、以下のような共通ルールがあります。
各コースの支給要件に加え、共通要件をすべて満たすことが申請の必須条件となっているため、よく確認しておく必要があります。
労働保険への適正加入が必須
助成金の対象となる事業主は、雇用保険・労災保険に適正に加入していることが条件です。未加入や保険料の滞納がある場合は支給対象外となります。助成金は「雇用を守る事業者」への支援であるため、法令遵守が前提となります。
就業規則や制度内容の明文化と周知
新しい制度を導入する際は、就業規則や社内規程に明記し、従業員へ周知していることが求められます。たとえば育児休業制度や介護短時間勤務制度などは、文書で定義されて初めて「制度導入」とみなされます。
取組内容の実施証拠を保存
助成金支給には、研修資料・社内メール・出勤簿・面談記録・制度運用実績など、実施を証明する資料の提出が必要です。提出後も支給決定日の翌日から5年間の保存義務があるため、証跡管理は慎重に行う必要があります。
虚偽申請・不正受給への厳格対応
虚偽の報告や実績の水増しなどが判明した場合、助成金の全額返還に加え、企業名の公表や刑事告発の対象となります。支給要領では、透明性・誠実性の確保を最重要項目として位置づけています。
他の助成金との重複支給は不可
同一の経費・同一の取組に対して複数の助成金を併用することはできません。ただし、目的が異なる取組
(例:時短支援と育児支援など)であれば併用可能です。申請前に労働局へ確認するのが安全です。
報告・申請期限の厳守
交付申請書や実績報告書の提出期限を過ぎた場合、いかなる理由でも不支給となりますので、期限は厳格に管理する必要があります。
電子申請について
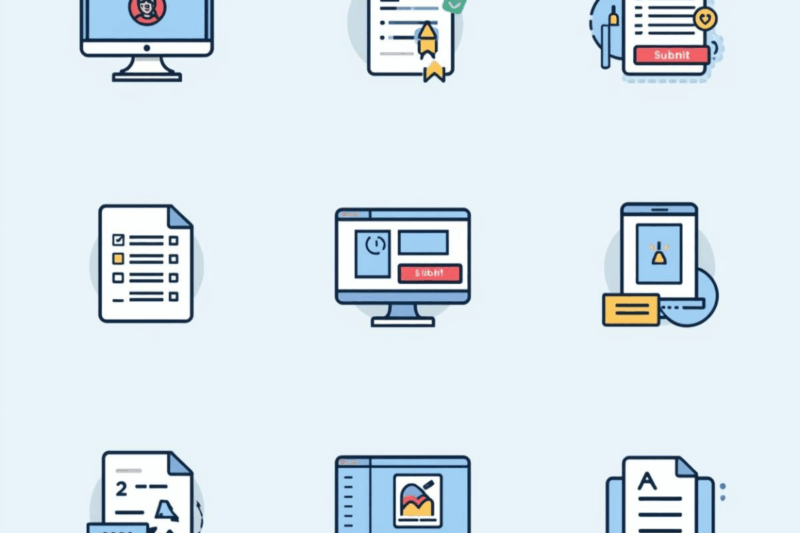
両立支援等助成金は、事業主本人、もしくは社会保険労務士や弁護士が代理申請することができます。郵送、もしくは電子申請で申請を行うことができます。
電子申請は令和5年度から開始しており、令和5年度以降の支給要領が適用される申請について利用可能です。適用される申請について、以下に具体的に記します。
出生時両立支援コース
- 第1種:令和5年4月1日以降に対象労働者の育児休業が開始した場合
- 第2種:令和5年4月1日以降に支給要件を満たした場合
介護離職防止支援コース
- 休業取得時/職場復帰時:令和5年4月1日以降に対象労働者の介護休業が開始した場合
- 介護両立支援制度:令和5年4月1日以降に対象労働者の介護両立支援制度の利用が開始した場合
育児休業等支援コース
- 育休取得時/職場復帰時:令和5年4月1日以降に対象労働者の育児休業が開始した場合(ただし、対象労働者が産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、令和5年4月1日以降に産後休業が開始した場合)
- 業務代替支援(現在は廃止):令和5年4月1日以降に対象労働者が育児休業から職場復帰した場合
- 職場復帰後支援(現在は廃止):令和5年4月1日以降に対象労働者が育児休業から職場復帰した場合
不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース
- 令和7年度以降の支給要領が適用される場合
育休中等業務代替支援コースと柔軟な働き方選択制度等支援コースに関しては、制度開始後全ての場合にて申請可能です。
なお、いずれも、コースごとに定める支給申請期間内の事案のみ申請が可能であることに注意してください。
FAQ(よくある質問)
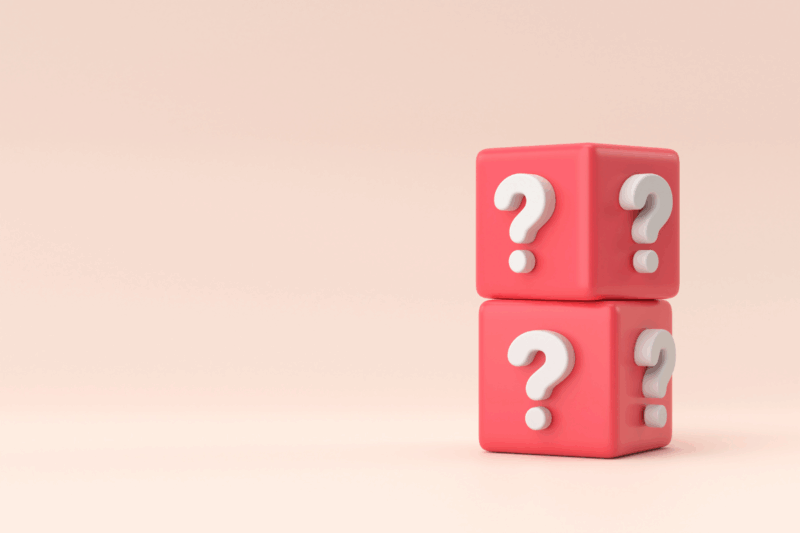
どのコースを選べばよいかわかりません。複数のコースを同時に申請することはできますか?
同一年度内で複数コースの申請は可能ですが、同じ取組・同一の従業員を対象とした重複申請はできません。たとえば、「育児休業等支援コース」と「育休中等業務代替支援コース」は目的が異なるため併用可能ですが、同一の育児休業取得に対して両方の助成を同時に受けることはできません。
申請前に「目的」「対象」「時期」が重ならないよう整理しておくことが大切です。
助成金を受け取るまでにどれくらい時間がかかりますか?
交付申請から実際の支給まではおおむね3〜6か月程度が目安です。
申請件数や審査状況によってはさらに時間がかかることもあります。助成金を資金繰りの充てにせず、余裕をもって計画的に進めることが重要です。「交付決定」を受ける前に制度を実施した場合は対象外になるため、必ず事前申請が原則です。
助成金を受けるために就業規則を改定しなければなりませんか?
はい。ほとんどのコースで、制度導入を就業規則や社内規程に明記し、労働者に周知していることが必須条件となります。
たとえば「介護休業制度」「不妊治療休暇制度」を導入する場合、就業規則に具体的な内容を追記したうえで、労働基準監督署に届出を行う必要があります。
他の雇用関係助成金(例:働き方改革推進支援助成金)と併用できますか?
原則として、同一の取組内容や同一経費についての併用は不可です。しかし、異なる目的の取組であれば併
用可能です。
たとえば、「働き方改革推進支援助成金で労働時間短縮」「両立支援等助成金で育児休業支援」というように、目的と経費が明確に区別されていれば同時活用できます。
まとめ
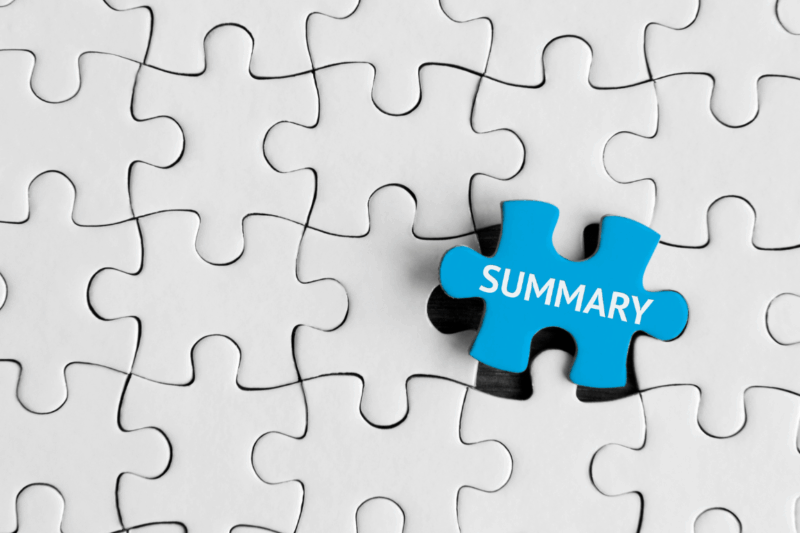
いかがでしたか?
本記事では、両立支援等助成金について、制度の概要や6つのコースについて解説してきました。
本助成金は、「従業員が安心して働き続けられる環境づくり」を支援する制度です。
うまく活用することができれば、企業、特に中小企業にとって、単に助成金を得るだけでなく、「離職防止」「人材定着」「採用力向上」という長期的な効果が期待できます。
人手不足対策や職場環境改善の第一歩として利用する価値が高い制度といえるでしょう。
申請すべきコースや申請手続き等に迷われた際は、ぜひシェルパ社会保険労務士法人やビジネス・カタリストをはじめとしたシェルパグループにお気軽にお声がけください。
本記事が両立支援等助成金についての理解を深めるうえでお役に立てますと幸いです。
補助金・助成金のご相談はシェルパ税理士法人へ いますぐ無料相談この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。
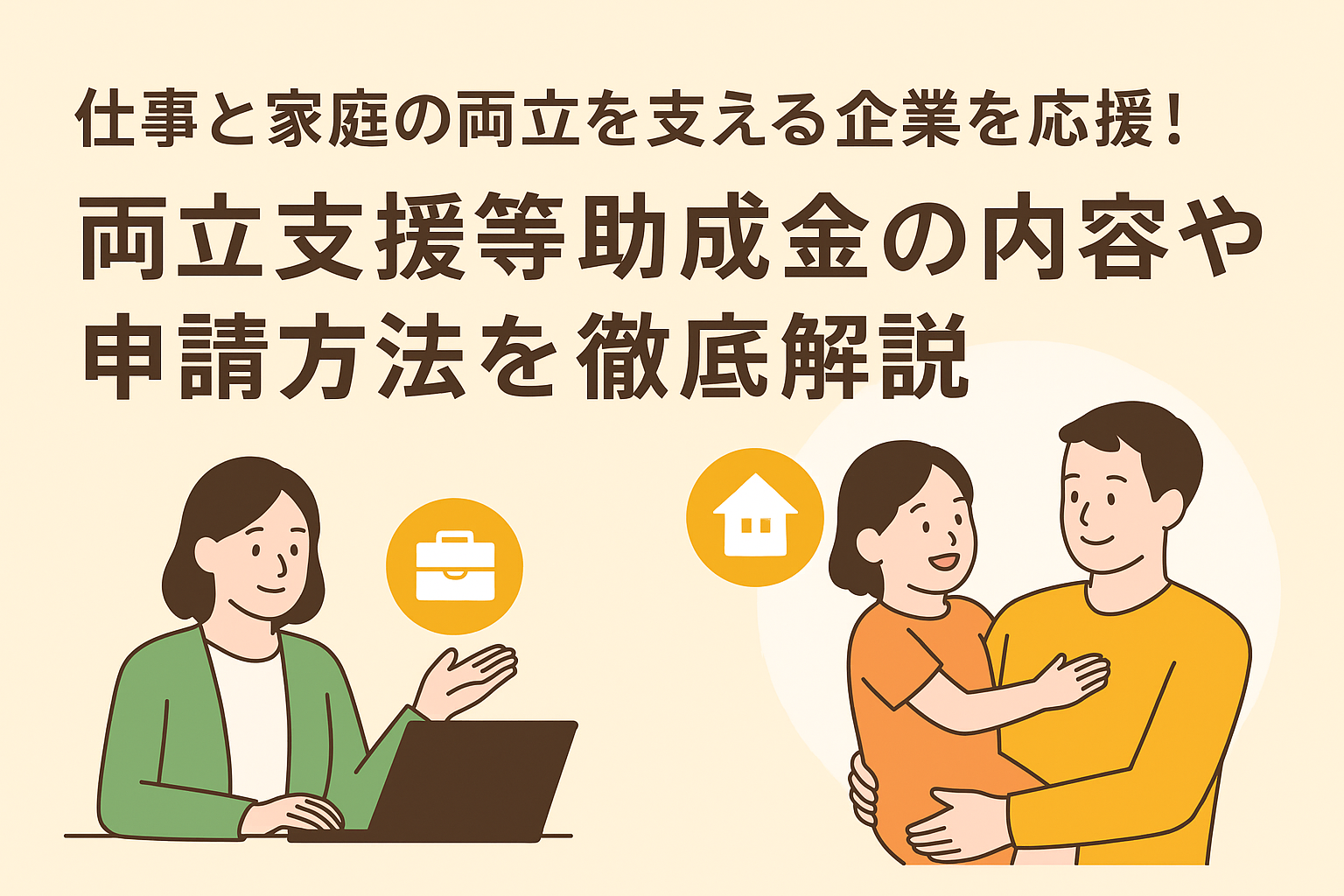



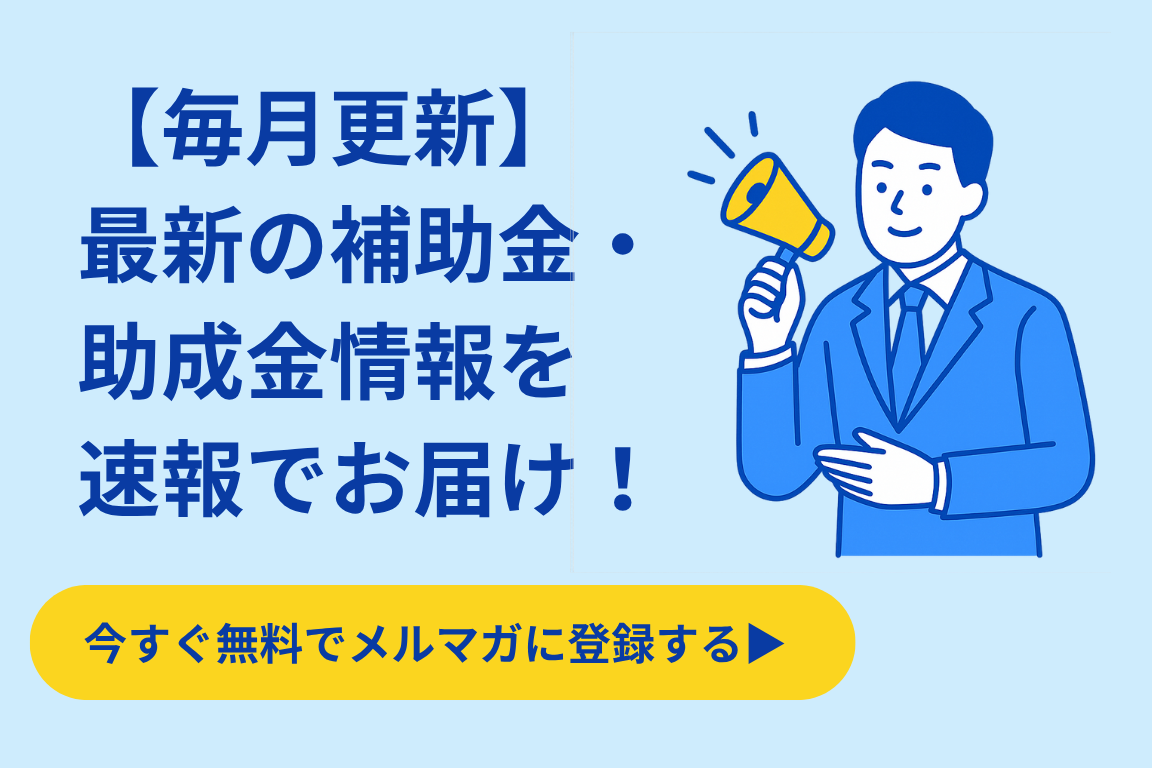
コメント