この記事を執筆・監修した人

- シェルパ税理士法人 資産税チームリーダー
相続税を専門とする大手税理士法人勤務後、2022年シェルパ税理士法人参画
財産評価による税額の圧縮や、迅速な税金計算、税額シミュレーションをもとにした相続人間の税額最適化などを得意とする。
中小企業の経営者の相続は、親族内で事業承継をおこなうことが多く、対象となる相続財産が会社の株式など事業承継に伴い扱いが難しい財産が多いため、家族間でトラブルに発展しがちです。
特に、事業の後継者と事業に関係のない他の相続人との間で利害が対立すると「争族」に発展してしまいます。
本記事では、経営者ならではの相続リスクと、相続トラブルを回避するためのポイントを分かりやすく解説します。
なぜ中小企業経営者の相続は揉めやすい?

中小企業の相続が揉めやすいのには、いくつかの理由があります。
中小企業経営者の場合、個人の金融資産よりも、自社の株式や会社の土地・建物など、事業に関連する資産が多くを占めます。この場合、公平性の観点からトラブルに発展することが多いのです。
ここでは、中小企業経営者の相続が揉めやすい理由を、順に確認していきましょう。
財産の大半が「会社」に偏っているから
中小企業の経営者の場合、個人の金融資産よりも、自社株式や会社の土地・建物など事業に関する資産が多くを占めているケースが少なくありません。なお、会社名義の資産は財産分与の対象外で、分割されるのは経営者個人の財産(例:保有する自社株)です。
この場合、遺産分割の際に「どのように株式を評価し、相続人全員の納得のもとに分けるか」といった難しい問題が発生することが多いのです。
現金や金融資産などの分割しやすい財産が少ないため、相続人同士で平等に分けることが難しく、不公平感が生まれやすくなります。
「後継者」と「他の相続人」に公平性の問題が生じるから
後継者としての役割を担う者は、日々の経営に携わっている一方で、他の相続人は必ずしもその状況を理解しているわけではありません。
こうした背景から、一方は「経営権を持っているのだから優遇されるべき」と感じ、他方は「自分たちも同じように扱われるべきだ」と思うことで、不公平を感じやすくなります。
また、事業承継は会社の代表者交代を指しますが、株式の譲渡とは必ずしも結びつきません。実際に株式移転をする際には、資金や納税が必要です。
この株式移転が相続と共に発生すると、納税資金をめぐりトラブルに発展しがちです。
事前の準備不足が「争族」の火種になるから
「遺言書があれば安心」と思われがちですが、内容が曖昧だったり法的に不備があったりすると、かえって相続トラブルを招くことがあります。
納税資金や生前贈与など、事前準備が不十分なまま相続が発生すると、残された家族は混乱し、感情的な対立に加え法律や税務の複雑な問題に直面することになります。
そのため、相続対策は元気なうちに始めることが何より重要です。
【具体例】よくある相続トラブル

では実際に、中小企業の相続ではどのようなトラブルが起こるのでしょうか。
経営権を巡る兄弟姉妹での対立や、自社株の評価額をめぐる意見の食い違い、納税資金の確保が難航するケースなど、さまざまな問題が発生します。
ここでは、実際にどのような相続トラブルが発生するのか、具体例をみていきましょう。
後継者と兄弟姉妹での対立
実際に、相続による企業の再編を契機に兄弟姉妹間での対立が生じ、経営権を巡って法的争いに発展するケースは後を絶ちません。
「会社を継いだ長男だけが得をしている」という不公平感から、他の相続人が遺留分侵害額請求をするケースや、他の兄弟姉妹が経営に関与したいと強く主張するケースがあります。
経営を引き継いだが納税資金が足りない
後継者が事業を継承し株式を相続しても、相続税の納税資金が不足するケースがあります。
たとえば、長男が経営を引き継いだものの、会社の資金繰りが厳しく、納税資金を得るために個人で借金をして納税を済ませたとしましょう。
この場合、長男は借金返済に追われることとなり、会社からの役員報酬を増額せざるを得ない状況になります。
本来、資金繰りが厳しかった会社の役員報酬を増額させたため、会社の資金繰りは更に厳しいものとなります。
このようなケースでは、代表者に借金があるので新たな融資を受けることもできず、最終的には倒産してしまう可能性もあるのです。
また、自社株式や土地・建物の評価が高額になることが多く、納税のために後継者の個人資産を売却せざるを得ない事態が発生することもあります。
経営者が残した遺言書が曖昧・無効
「会社を長男に継がせる」などの簡単な遺言は、トラブルのもとです。
たとえば、土地・建物の名義区分で解釈が分かれる、会社が特定できず相続できないなどの理由から裁判に発展することが多々あります。
また、自筆遺言で日付や押印の不備により無効となり、法定相続分での再分配を余儀なくされたケースや、株式の配分割合・評価方法が不明確なために遺留分請求が起きた事例もあります。
遺言は、具体的かつ正確な記載が必要なため、公証人役場にて公証人に作成してもらう公正証書遺言を作成していると安心です。
揉めないための「3つ」の対策
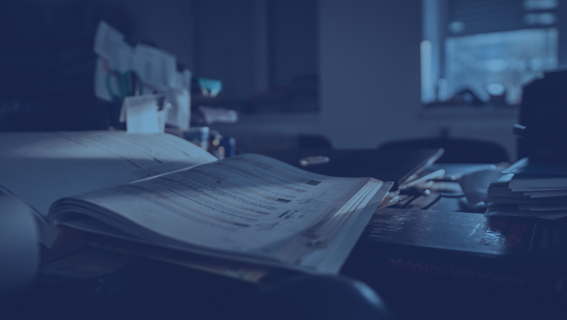
相続トラブルを回避するために、中小企業の経営者はどのような対策を講じるべきでしょうか。
争族にしないために、以下の「3つ」の対策をしておきましょう。
① 現状の「資産と経営権の可視化」
相続対策の第一歩として、自社の資産・負債・経営権の状況を可視化することが重要です。
自社株式、事業用不動産、機械設備、預貯金、生命保険などすべての資産をリストアップし、評価額を把握しましょう。
特に、自社株式については、株式保有状況や経営権の所在を明確にする必要があります。これらの作業により相続時の評価がスムーズになり、相続人間での公平性も確保できます。

② 家族との「定期的な対話」
相続において「家族との対話」はとても重要です。経営状況や相続の意向を透明にすることで、トラブルを防ぐことができます。
スムーズな相続のためには、後継者の選定や財産の分配、納税資金の準備について、家族全員で話し合うことが求められます。
特に、会社を継がない相続人の意向を尊重し、生活設計についても配慮することが大切です。
「お金の話はしたくない」と感じるかもしれませんが、リラックスした場で少しずつ話題にするのが効果的です。早めの話し合いで、争いを未然に防ぎましょう。
③ プロを交えた「早めの対策」
相続対策には税理士、弁護士、司法書士などの専門家の助言が不可欠です。
専門家は会社の状況や家族構成に合わせ、遺言書作成、生前贈与、生命保険活用、事業承継対策など、最適な方法を提案してくれます。
特に、中小企業経営者の場合は会社の存続にも関わるため、専門家の支援を得て家族間の対立を防ぎ、円滑な承継を目指すことが重要です。
まとめ|今すぐ始めるべき「生前対策」の第一歩

相続問題は未来のことと思われがちですが、早期の対策が重要です。まずは現状の整理から始め、遺言書作成や専門家との相談を進めましょう。
前述したとおり、中小企業は相続が会社の存続にも影響を及ぼすため、生前対策がとても重要です。
「まだ大丈夫」「うちは大丈夫」と気を抜くのは危険で、どんなに仲の良い家族でも対立する可能性があります。
早めの準備が「争族」を防ぎ、会社や家族の未来を守る基盤となるのです。
次回は「自社株式の評価と承継の具体的手法」を解説します。
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。
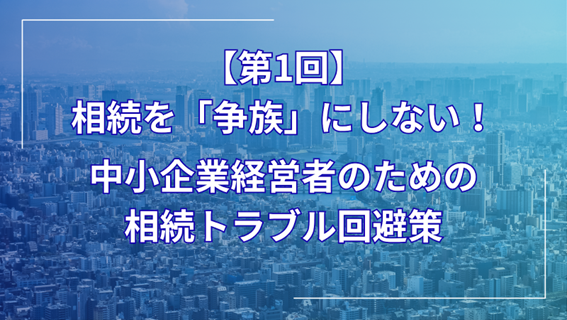

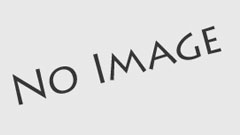
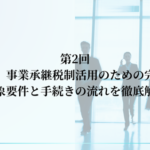
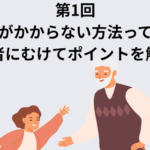
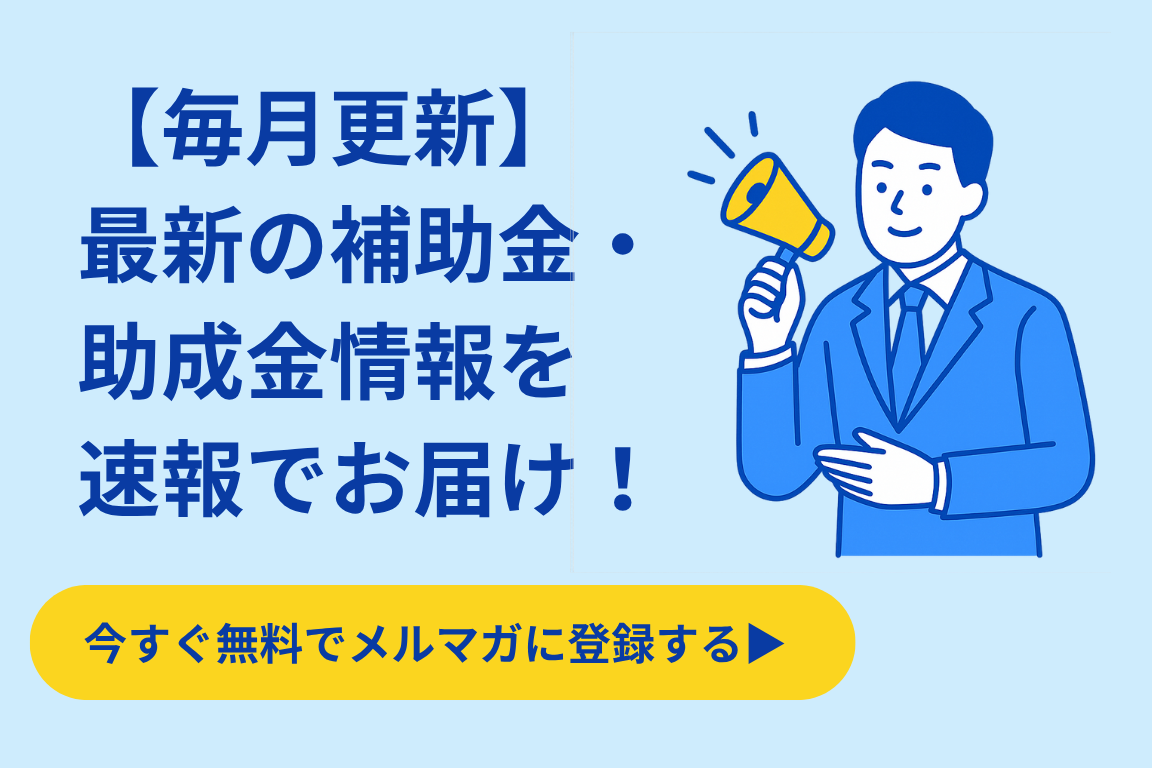
コメント