目次
この記事を執筆・監修した人

- シェルパ税理士法人 パートナー 公認会計士・税理士・MBA(国際経営学)
四大監査法人の一つに勤務後、米国へのMBA留学を経て、2013年に参画、2016年の税理士法人立ち上げよりパートナー
上場準備会社のIPOプロジェクトの責任者として実際の上場まで従事した経験を持ち、国際税務やM&Aにかかる会計税務も専門とする。
 メルマガ挨拶文2025/12/242025年12月メルマガ挨拶文
メルマガ挨拶文2025/12/242025年12月メルマガ挨拶文 メルマガ挨拶文2025/11/272025年11月メルマガ挨拶文
メルマガ挨拶文2025/11/272025年11月メルマガ挨拶文 メルマガ挨拶文2025/10/282025年10月メルマガ挨拶文
メルマガ挨拶文2025/10/282025年10月メルマガ挨拶文 M&A2025/9/26クロスボーダーM&Aにおける税務デューデリジェンスの重要性
M&A2025/9/26クロスボーダーM&Aにおける税務デューデリジェンスの重要性
クロスボーダーM&Aでは、国際税務の見地からの税務デューデリジェンスを行い、税務面でのリスクを洗い出すことが非常に重要になります。
M&Aにおける税務デューデリジェンスの役割やクロスボーダーM&A特有の問題について解説します。
クロスボーダーM&Aとは何か

M&Aとは、企業の合併と買収のことです。合併は二つ以上の会社が一つの会社にまとまること、買収は資金力のある会社が魅力的な事業を行う会社を丸ごと買い取ることを意味します。
そして、クロスボーダーというのは、国境を超えるという意味で譲渡企業(売り手)と譲受企業(買い手)のどちらかが海外企業である場合を意味します。
近年、日本でもM&Aが盛んになっています。
M&Aは、大企業の事例が目立ちますが、中堅企業や中小企業でも積極的に行っているケースが増えています。クロスボーダーM&Aも増加傾向にあり、特にASEAN地域の企業とのM&Aが増加しています。
M&Aは、国内企業同士でも統合プロセスが複雑で容易ではありませんが、海外企業とのM&Aは、それぞれの国により法制度や税制度が異なることから、さらに複雑になり、専門家のサポートなしでは実現が難しいことが多いです。
クロスボーダーM&Aの2つのパターン
クロスボーダーM&Aは、譲渡企業(売り手)と譲受企業(買い手)のどちらが海外企業なのかにより、次の2つのパターンに分類できます。
- イン・アウト(In-out)型(アウトバウンド型):日本企業が海外企業を買収する形のM&Aのこと
- アウト・イン(OUT-IN)型(インバウンド型):海外企業が日本企業を買収する形のM&Aのこと
クロスボーダーM&Aの具体的な手法
クロスボーダーM&Aの具体的な手法としては、
- 株式譲渡
- 事業譲渡
の2つが挙げられます。
株式譲渡
株式譲渡とは、譲渡企業(売り手)の株主が保有する株式を譲受企業(買い手)に譲渡することにより、譲受企業(買い手)に経営権限を移転させる方法のことです。
譲受企業(買い手)は、譲受企業(買い手)の資本はもちろん、負債もすべて承継するため、財務や事業はもちろん、法務や税務面も含めた実態調査(デューデリジェンス)を行うことが非常に重要になります。
また、国によっては外資規制により、買収できる規模に制限が設けられていることがあるため、あらかじめ確認する必要があります。
事業譲渡
事業譲渡とは、譲渡企業(売り手)の事業部門の全部または一部を切り離したうえで、譲受企業(買い手)に譲渡する方法です。
譲受企業(買い手)は、譲渡企業(売り手)の会社を丸ごと買い取るわけではなく、欲している事業部門のみを買い取ることができます。
一方、譲渡企業(売り手)も、手放したい事業だけ譲渡し、注力したい事業部門は残すことも可能です。
どちらの企業にとってもメリットがありますが、権利義務関係を個別に移転しなければならないため、手続きが煩雑になります。
税務デューデリジェンスとは何か

M&Aでは、譲受企業(買い手)は、譲渡企業(売り手)の会社や譲り受ける事業部門の実態を調査するために、様々な実態調査(デューデリジェンス)を行います。
この中でも、税務に特化した実態調査のことを税務デューデリジェンスと言います。
税務デューデリジェンスでは、譲渡企業(売り手)の過去の税務申告書や税務調査の関連資料を入手したうえで納税状況や税務申告の正確性を調べます。
なお、財務デュー・デリジェンスについてはこちらの記事で解説していますので併せてご覧ください。
税務デュー・デリジェンスを行う目的
税務デューデリジェンスを行う目的は税務リスクを把握し、税務リスクをM&Aの取引価格に反映させたり、M&Aの可否を判断することです。
譲渡企業(売り手)に税務申告の漏れや誤りがあった場合、M&A後は、譲受企業(買い手)が税務申告の修正や納税の負担を追うことになります。
税務デューデリジェンスにより、追徴課税される額を見越したうえで、M&Aの取引価格や条件を見直したり、M&Aそのものを断念する等の判断を行います。
また、譲渡企業(売り手)の繰越欠損金を引き継ぐことにより、譲受企業(買い手)の課税額が減少する場合もあるため、その見通しについても明らかにします。なお、節税目的のM&Aは基本的に認められていないため、その可否も判断する必要があります。
税務デューデリジェンスを行うタイミング
税務デューデリジェンスを行うタイミングは、企業間でM&Aの基本合意を成立させた後、最終条件の交渉に入る前の段階で行います。
M&Aを持ち掛けられた時点で、税務デューデリジェンスを実施するのは、譲渡企業(売り手)に対して失礼ですし、逆に、最終合意が成立した後で、実施しても、調査結果を踏まえた価格や条件の交渉ができなくなります。
そのため、基本合意後、最終条件の交渉に入る前という限られたタイミングで実施することが重要と言えます。
クロスボーダーM&Aにおける税務デューデリジェンスの役割
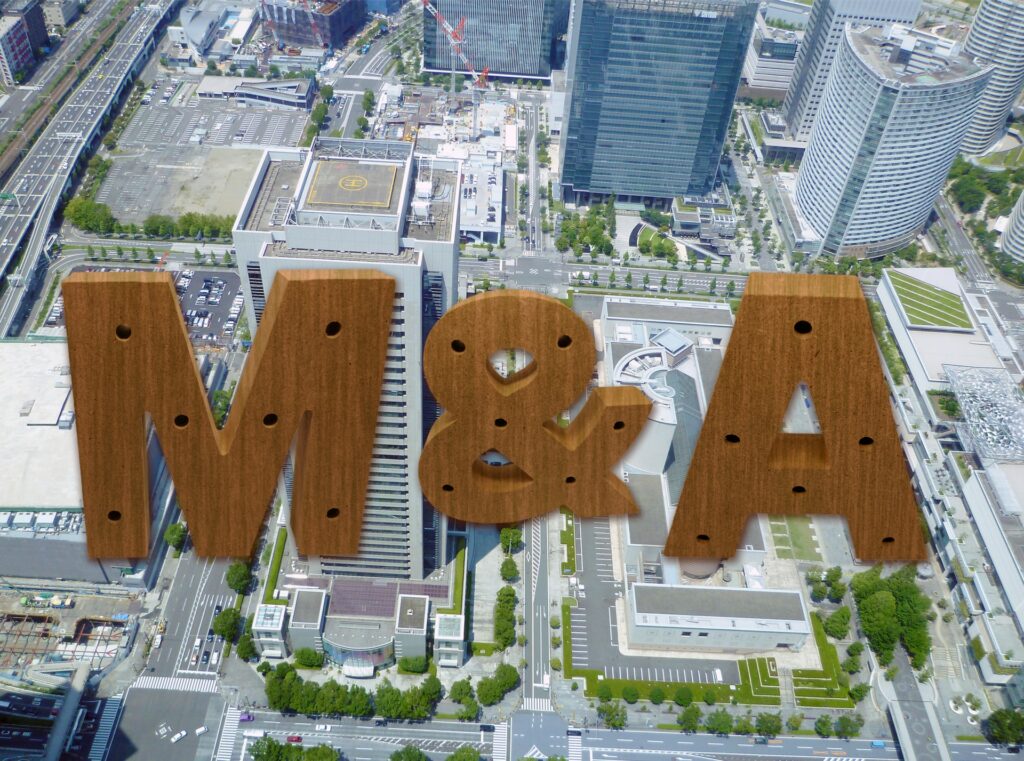
クロスボーダーM&Aでは、税務デューデリジェンスがより重要な役割を果たします。
国内だけで完結するM&Aでは、日本の税制のみに基づいて調査を行えば足りますが、クロスボーダーM&Aでは、海外企業の国・地域に適用される税制も踏まえた調査が必要になるためです。
また、グローバル・ミニマム課税を初めとする国際的な合意に基づく課税制度も存在するため、より慎重な調査が求められます。
クロスボーダーM&Aにおける税務デューデリジェンスの内容

M&Aにおける税務デューデリジェンスは、譲渡企業(売り手)の次の税目を対象に行います。
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 特別法人事業税
- 消費税
- 地方消費税
- 源泉税
- その他の税目
この中でも特に重要になるのが、税額の大きい法人税です。
クロスボーダーM&Aでも調査すべき税目は同じで、海外の税制に基づき、法人税に相当する税目を中心に調査します。
調査すべき項目は次のような点です。
- 過去の税務申告が適正に行われており、納税義務が履行されているか
- M&A後に多額の課税負担がかかる潜在的なリスクがあるか
- 繰越欠損金が発生するか、また、譲受企業(買い手)が引き継ぐ可能性があるか
- 外国子会社合算税制、移転価格税制、過少資本税制、過大支払利子税制といった国際課税への対応の必要性
海外の税制については、日本の税理士だけでは限界があるため、海外の税制に詳しい現地の税理士等の協力が必要になることもあります。
また、譲渡企業(売り手)に子会社がある場合は、子会社についても調査を行う必要があります。
多国籍企業の場合は、子会社が日本を含め複数の国に存在していることもあり、広範な調査が必要になります。
まとめ

国内でのM&Aでは、実施に先立って、様々な実態調査(デューデリジェンス)を行うことはよく知られていますが、その必要性はクロスボーダーM&Aでも同じです。
クロスボーダーM&Aの場合は、海外の税制を基に調査を行う必要がありますし、国際課税への対応の必要性についても検討しなければなりません。
税務デューデリジェンスをおろそかにしたまま、クロスボーダーM&Aを実施してしまうと、後に多大な税務リスクが露呈することがあります。
クロスボーダーM&Aをご検討しているなら国際税務に詳しい税理士へご相談ください。

お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

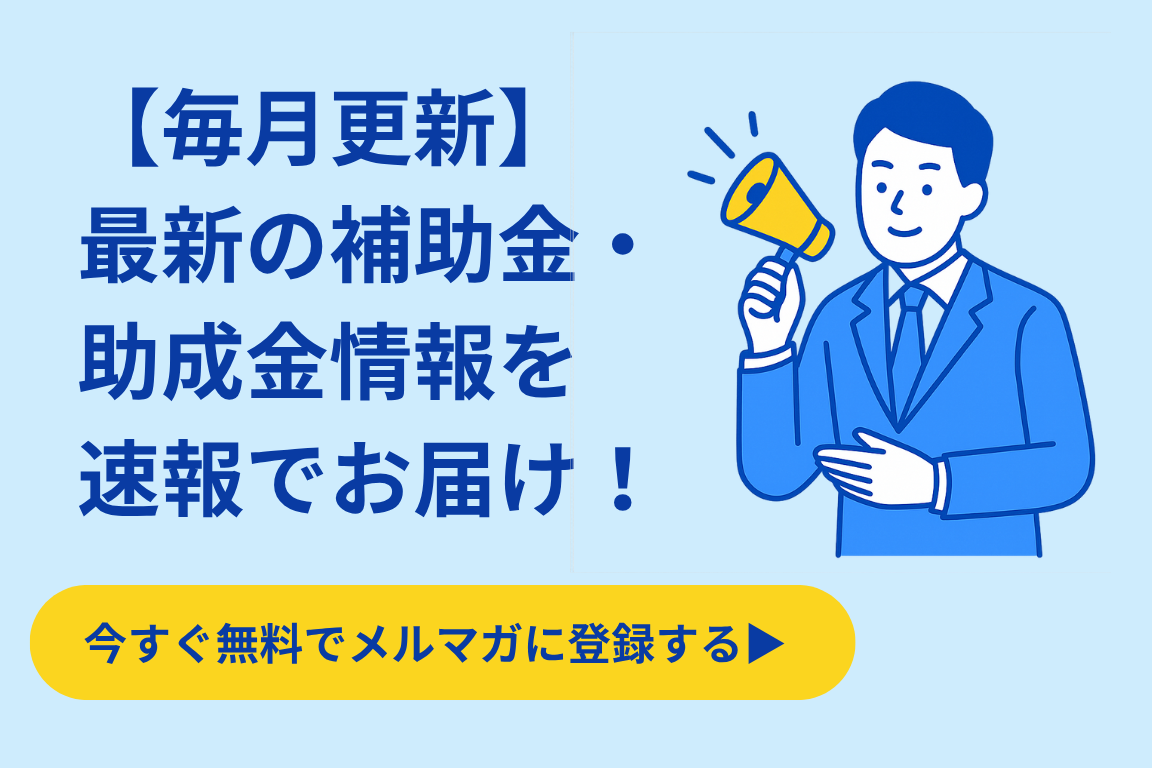
コメント