目次
この記事を執筆・監修した人

- シェルパ税理士法人 パートナー 公認会計士・税理士・MBA(国際経営学)
四大監査法人の一つに勤務後、米国へのMBA留学を経て、2013年に参画、2016年の税理士法人立ち上げよりパートナー
上場準備会社のIPOプロジェクトの責任者として実際の上場まで従事した経験を持ち、国際税務やM&Aにかかる会計税務も専門とする。
 メルマガ挨拶文2025/12/242025年12月メルマガ挨拶文
メルマガ挨拶文2025/12/242025年12月メルマガ挨拶文 メルマガ挨拶文2025/11/272025年11月メルマガ挨拶文
メルマガ挨拶文2025/11/272025年11月メルマガ挨拶文 メルマガ挨拶文2025/10/282025年10月メルマガ挨拶文
メルマガ挨拶文2025/10/282025年10月メルマガ挨拶文 M&A2025/9/26クロスボーダーM&Aにおける税務デューデリジェンスの重要性
M&A2025/9/26クロスボーダーM&Aにおける税務デューデリジェンスの重要性
財務デュー・デリジェンスは、企業の買収などに際して、対象企業の財務状況を詳細に調査・分析するプロセスを指します。この調査は、過去および現在の財務状態、経営状況やキャッシュフローの状況などを包括的に評価することで、買収における留意点を把握することを目的としています。財務デュー・デリジェンスは、潜在的なリスクや問題点を明らかにし、投資判断の精度を高めるために不可欠なステップです。
また近年では、M&Aの成功をより確かなものとするべく、中小企業のM&AにおいてもPMI(Post Merger Integration)をするケースが増えてきており、財務デュー・デリジェンスと同時進行で行うこともあります。
本稿では財務デュー・デリジェンスの概要や必要性、留意点について、税務デュー・デリジェンスについても言及しながら解説します。
財務デューデリジェンスの重要性

財務デュー・デリジェンスは、企業買収におけるリスク評価や投資判断の精度向上に不可欠です。過去および現在の財務状態を詳細に分析し、潜在的なリスクや問題点を明らかにすることで、買収の是非の判断や、買収前にやっておくべきことの整理、買収後の計画策定や経営戦略の立案に重要な情報を提供します。
近年、日本における事業承継の必要性なども関連して、中小企業でもM&Aが増加しており、財務・税務デュー・デリジェンスの重要性が高まっています。これにより、中小企業のM&Aにおいても、潜在的なリスクを事前に把握し買収後の成功確率を上げるための戦略的な判断が求められます。
財務・税務デュー・デリジェンスの基本

目的と範囲
財務・税務デュー・デリジェンスの目的は、企業買収において過去および現在の財務状態や税務の状況を詳細に分析し、潜在的なリスクや問題点を明らかにすることです。その範囲には収益性分析、財務状態分析、運転資本分析、キャッシュ・フロー分析、会計処理の妥当性検証、および税務面での調査が含まれます。
財務デュー・デリジェンスは一般的には公認会計士をはじめとした会計事務所により行われることが多いですが、税務デュー・デリジェンスにおいては税理士が関わりますし、弁護士が法務デュー・デリジェンス、社会保険労務士が労務デュー・デリジェンスを担当するなど、士業が連携して実施することもあります。
一方でビジネスデュー・デリジェンスについては、コンサルタントが協力することもありますが、自社の事業とのシナジー効果などの測定が関わることもあり、買い手企業において行うこともあります。
実施タイミングと期間
財務・税務デュー・デリジェンスは、企業買収の初期段階で開始されるべきです。通常、買収交渉が進展し、基本合意に達した後、詳細な調査が行われます。企業の規模や複雑さにより異なりますが、数週間から数か月に及ぶことが一般的ですが、M&Aは買い手(競合)が多かったり、様々な要因から早期の判断を求められることも多く、デュー・デリジェンスも比較的短期間で集中して報告まで至るケースも多いです。
調査結果は、最終的な投資判断や買収契約に大きな影響を与えます。
財務面の重点調査ポイント

収益性分析(売上・利益の質の精査)
収益性分析では、売上の推移や利益率の変動を詳細に確認し、その持続可能性や再現性を評価します。特に、売上の構成要素や主要顧客の依存度、季節変動の影響、異常な売上高の発生要因などを検討することで、収益の安定性を判断します。また、利益の質についても、一次的な費用削減や非経常的な要因によるものか、持続可能なものかを見極めることが求められます。
財務状態分析(資産・負債の実態把握)
財務状態分析は、企業の資産と負債の実態を詳細に把握することを目的としています。具体的には、企業が保有する資産の評価や、その資産がどの程度の価値を持つかを確認します。また、負債についても、その規模や返済能力、期限などを詳細に調査し、企業の財務的な健全性を評価します。また、いわゆる簿外負債などが無いかについても調査します。これにより、企業の財務状態が健全であるか、潜在的なリスクが存在するかを明らかにし、買収後の戦略策定や買収額の算定に役立てます。
運転資本分析
運転資本分析は、企業の日常業務に必要な資金の流れを評価するために行われます。具体的には、売掛金、在庫、買掛金などの項目を詳細に調査し、資金繰りや流動性、効率性を分析します。これにより、運転資本の健全性や改善の余地を把握し、買収後の資金計画や経営戦略策定に役立てます。
キャッシュ・フロー分析
キャッシュ・フロー分析は、企業の現金の流れを把握し、その経営の健全性を評価するために行われます。具体的には、営業活動、投資活動、財務活動の各キャッシュ・フロー(CF)を把握し、現金収支のバランスや変動要因を分析します。企業の持続のための資金が本業から稼げているのか(営業活動によるCF)、資産の売却などから得ているのか(投資活動によるCF)、または借入や増資などから得ているのか(財務活動によるCF)などを判断し、対象会社の資金獲得能力を把握します。
会計処理の妥当性検証
会計処理の妥当性は、財務デュー・デリジェンスの一環として、日本の中小企業においては重要な検証事項といえます。日本の中小企業は主に税務会計による財務諸表の作成がなされており、上場会社などとは異なる基準での財務数値であることから、企業の実態や比較可能性が担保されないおそれがあるためです。
また税務会計においては企業会計では認められない処理もあるため、あるべき帳簿価額になっていない可能性もあるため是正を要することがあります。例えば中小企業の会計においては利益状況次第で減価償却費を計上しない、という判断が認められることもあり、その場合には法定の償却方法で、定められた耐用年数にわたって減価償却をしていた場合の帳簿価額の理論値を算出して財務諸表の数値を調整するなどの処理が必要になります。
税務面の重点調査ポイント

税務コンプライアンスの状況
税務コンプライアンスの状況に関する調査では、対象会社が税法等に準拠して税務申告を行っているかや税務上の義務を履行しているかを確認します。具体的には、申告内容の正確性、適時性、適法性を評価し、潜在的なリスクを洗い出したり、顕在化していない税務上の義務の不履行が無いかなどを確認したりします。
また、過去の税務調査履歴や指摘事項を検証し、現在の税務ポジションが適切かどうかを判断します。この調査は、買い手や対象会社の税務リスクを最小化し、将来の税務問題を回避するために非常に重要です。
タックスプランニングの評価
タックスプランニングの評価は、企業が現行の税務制度を最大限に活用し、合法的に税負担を最小化する戦略を立案・実行しているかを検証するプロセスです。これには、税制変更への対応、利用できる税額控除制度の利活用、節税スキームの適用状況、将来の税務戦略の有効性の評価が含まれます。適切なタックスプランニングは、企業の財務健全性を維持し、長期的な成長を支える重要な要素となりますし、現状で適用できていない優遇税制が見つかった場合には、潜在的な有利性として認識することもできます。
繰越欠損金等の税務資産の評価
繰越欠損金等の税務資産の評価は、企業が過去の損失を将来の利益に対して繰り越し、税負担を軽減するための重要なプロセスです。この評価を通じて、損失の繰越が将来の課税所得にどのように影響するかを見極め、税務戦略の一環として活用します。適切に評価された繰越欠損金は、企業の財務健全性を高め、将来の税負担を最適化するための有効な手段となります。
ただし、M&Aの対象会社の繰越欠損金を活用できるかに対しては様々な制約や条件があるため、買収後に実際に繰越欠損金を活用して税金対策をできるかどうか、できない場合でも代替策が無いか、M&Aに精通した税務の専門家を交えながら戦略を練ることが肝要です。
会計事務所の総合的な支援体制

財務・税務の専門的知見の統合的活用
財務・税務デュー・デリジェンスにおいては、上述の通り、総合的な専門性を基にした多方面からの検証が求められます。会計・税務・財務のそれぞれにおいて専門性を持っているだけではなく、その周辺業務に対しての知見や理解が求められますし、デュー・デリジェンス自体の知識も要します。特定の分野に特化した専門家ではなく、総合的な経験や知識を持つ専門家であることが求められる領域であるといえます。
クロスボーダー案件での国際ネットワーク活用
財務・税務デュー・デリジェンスにおいて、クロスボーダー案件での国際ネットワークの活用は重要です。
これにより、企業はグローバルな専門知識を活用し、複雑な国際規制や税務問題に対応できます。 各国で税制や会計基準は異なるため、たとえ日本の専門家であったとしても、他国での適正性や適法性などは評価することが難しいためです。
なお、シェルパ税理士法人は国際的な会計事務所のネットワークの一つであるJPA Internationalに所属し、日本の代表窓口も担っているため、海外の会計事務所と連携をとりながらのサービス提供が可能です。
ポストディールサポートまででの一貫支援
財務・税務デュー・デリジェンスにおける会計事務所の一貫支援は、クロスボーダー案件での国際ネットワークの活用やポストディールサポートまで含めて、企業の長期的な財務健全性と成長を支援します。
これにより、企業は潜在的なリスクを早期に特定し、適切な対策を講じることができ、統合プロセスの円滑化が図れます。
これには後述のPMIのような業務も含まれます。
PMIを同時進行で進めることの重要性

財務・税務デュー・デリジェンスにおいてPMI(Post Merger Integration)を同時進行で進めることは、企業統合の成功において極めて重要です。
PMIは、買収後の企業の統合プロセスを指し、プロセス改善、組織文化の統合、およびシステム連携を含む一連の活動を意味します。デュー・デリジェンスの段階でPMIの計画を並行して進めることで、統合後の実行スピードが向上し、シナジー効果を早期に実現させることが期待されます。
加えて、潜在的なリスクや課題を事前に特定し、適切な対策を立案することで、統合プロセスの円滑化が図られます。これにより、財務的な安定性を保ちつつ、企業価値の最大化を目指すことが可能となります。
シェルパグループでは、一般的に大企業で行われるような年単位でのPMIではなく、中小企業のM&Aにフォーカスしたより簡便的なPMIである、フージョンビズというサービスも提供しております。
PMIの詳細はこちらで解説していますので、あわせてご覧ください。

PMI とは? M&A における重要性や取り組み方について解説
おわりに

今後の展望
我が国においては事業承継の選択肢の一つとしてのM&Aが益々注目されていくことが予想されています。また、ベンチャー企業のエグジット(一旦のゴール)として、上場だけでなくM&Aを選択肢とするケースも増えてきています。これによりM&Aが行われる事例は今後増えていくことが想定されていますが、M&Aが成功する確率はそれほど高くないのも実情です。
それでも、M&Aの前段階としてのデュー・デリジェンスや、後工程としてのPMIなどの業務をきちんと行うことで、M&Aの成功確率を上げていくことは十分に可能と考えられ、今後その重要性は増していくと予想されます。
早期からの専門家関与の重要性
財務・税務デュー・デリジェンスにおいて、早期から専門家が関与することは極めて重要です。専門家の早期関与により、潜在的なリスクや課題を迅速に特定し、適切な対策を講じることが可能となります。また、早期から専門家が関与することにより、売り手と買い手の双方にメリットを持たせられるスキームを構築することも可能になります。
これにより、統合プロセスが円滑に進行し、企業価値の最大化が図れます。また、専門家の知見を活用することで、より正確なリスク評価が行え、意思決定の迅速化が実現します。早期からの関与は、企業統合の成功に向けた重要なステップとなります。
シェルパグループでは、対象企業の適切な評価や課題の洗い出し、M&Aを成功に導くための統合プロセスのお手伝い、さらにはM&Aに際しての予算策定やその後の予実管理や専門性の高いM&Aの会計・税務処理などをサポートしております。
M&Aを検討される際にはぜひお手伝いさせていただきたいと思いますし、早ければ早いほどより有効なサポートをさせていただけると考えております。お気軽にお問い合わせいただけましたら幸いです。
財務デュー・デリジェンスについてのご相談はこちらからお受けいたします。
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

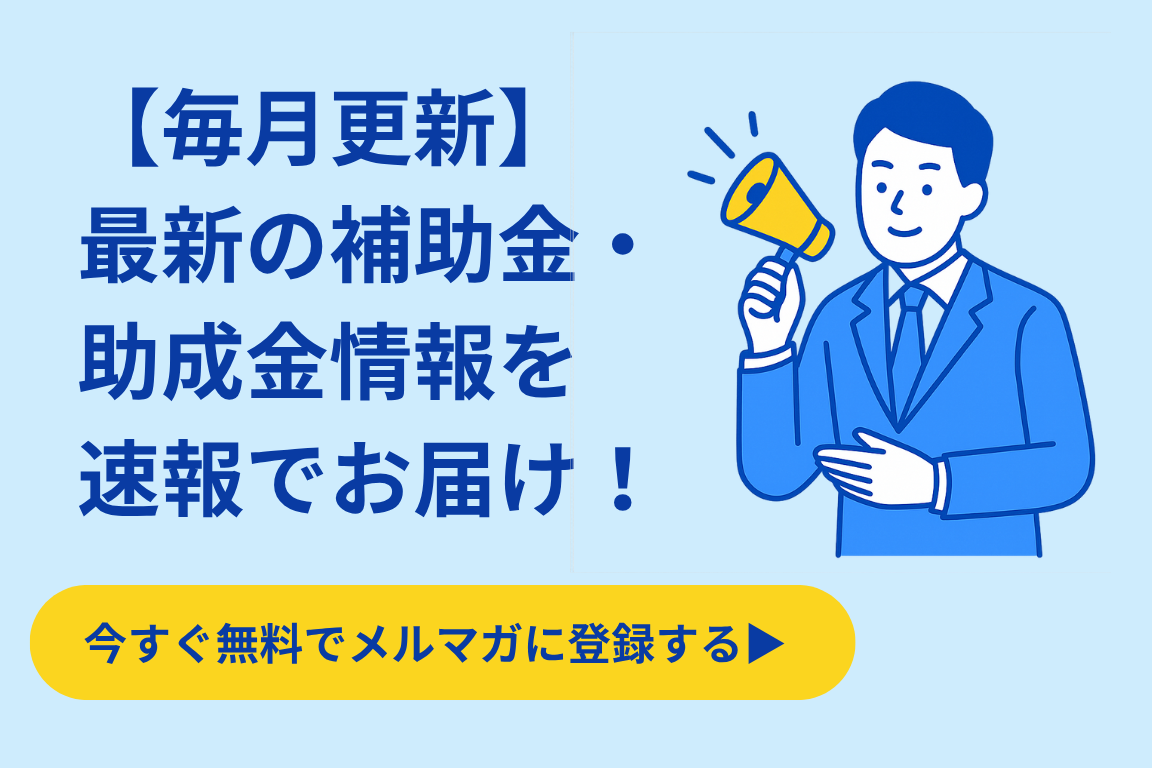
コメント